渡嘉敷村の歴史
大昔の慶良間諸島(地質時代)慶良間の島々のなりたち
渡嘉敷島の最高峰、赤間山の山頂に登って周囲の島々を見渡すと、北の海上には、伊江島、粟国島、西方には座間味島をはじめ、阿嘉島、慶留間島、久場島、屋嘉比島。晴れた日には、遠く西の海上に、渡名喜島、久米島も見ることができます。又、東には、沖縄本島が南から北に、海上に縄を浮べたように横たわっています。
これらの島々は、現在、海で隔てられていますが、今から200万年から2万年ほど前にかけて陸続きになったり、島々に分かれたりと変動をくりかえしたのです。
氷河時代
今から200万年から2万年ほど前、地球上には四、五度、とても寒い気候がおとずれました。この時代を氷河時代と呼んでいます。さむい時期を氷期、暖かい時期を間氷期と呼んでいます。氷期には、南極や北極をおおっている氷の量も増えて、その分だけ、海の水が少なくなるわけです。だから、氷期は、海面がずっと下がります。
ギュンツ氷期
新生代第四紀の始め、ギュンツ氷期の時代(150万~200万年前)年平均気温が現在より8~10度も低かった時代には、沖縄本島から久米島にかけて大きな陸地が広がっていました。その中央付近に慶良間の島々があり、1500から2000メートルをこすような山々がそびえていました。
その当時、西の方の久米島付近や北の方の粟国島近海には活火山があり、さかんに活動し、火山灰や溶岩を噴出していました。その火山灰の一部は、西風や北風にのって、慶良間の山々や沖縄本島にも降ったことでしょう。
ミンデル氷期
50万年前のミンデル氷期の頃になると、1500から2000メートル以上あった慶良間の島々もしだいに沈降し、数百メートルの高さになりました。
東の方の那覇や糸満をはじめ、中頭から島尻の地域には浅い海が広がり、そこには、いろいろな種類のサンゴが群生し、美しいサンゴ礁をつくっていました。
ウルム氷期
約2万年前は、四、五度おとずれた氷期の中で、いちばん最後にあたる氷期で、ウルム氷期と呼ばれている時代です。この氷期には、海水面が現在の海水面より、80~140メートル程低かったのです。このことは阿波連の西方、500~600メートル、水深50メートルから60メートルの海底に平坦面があり、その中央に北から南へ海底谷(古川道)が発達していることからわかります。
また、太陽光線のとどく海面近くでしか成長しないサンゴや石灰藻、その他、サンゴ礁をつくる有孔虫などの生物の遺骸などが堆積してできたサンゴ石灰岩(琉球石灰岩)が、70~80メートルの海底でも見つかっています。ということは、50万年前に堆積したサンゴ石灰岩層(琉球石灰岩層)は、慶良間の島々と共に70~80メートルも沈没を続けたと考えることができます。
ところで、海水面が80~140メートルも低くなるとどうでしょう。現在、村営定期船が往復している泊から渡嘉敷までの海の水深は、平均60~70メートル前後、慶良間海峡が50~60メートル、渡嘉敷島から約60キロメートル離れている久米島との間の海さえ100メートル前後しかありません。
80メートルから140メートルも海面が下がったとすると、島々は、ほとんど陸続きになるのです。時は流れ、2万から3万年前、沖縄本島から慶良間諸島を通り久米島まで陸続きだった頃、沖縄の島々にも北や南の島々から、陸づたいに、あるいは、いかだや舟に乗って、人々が住みつくようになりました。
大昔の人々
2万年前は旧石器時代にあたり、沖縄本島には、山下町洞人や港川人が住んでいた時代です。その頃の人々は、慶良間諸島や久米島にまで広がる陸地を、食物を求めて移動したことでしょう。
その後、海面は、地殻変動(島々の隆起や沈降等)や気候の変動による上がり下がりをくりかえしながら、しだいに上昇していったのです。6000年ほど前には海面変動は停止し、現在のような島の群れになりました。島が群れをなしているように見える慶良間は、別名「群れ島」と呼ばれていた時代もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
渡嘉敷村役場
沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷 183
電話:098-987-2321
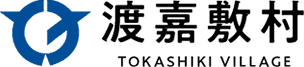


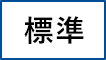
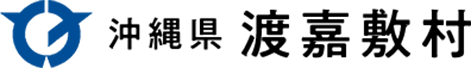
更新日:2024年03月26日